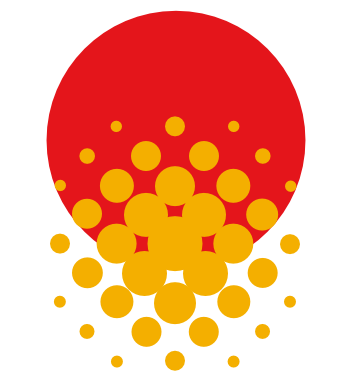2025.11.12
社労士事務所において就業規則等の作成支援クラウドソフトウェアの導入費用は支給対象経費となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
運営会社がクラウド上のソフトウェアの更新や管理を行うのみで、社労士等が本サービスを利用することにより、自ら規則の作成等が行える仕様であれば問題ありませんが、本サービスに情報を入力することにより、当該情報をもとに、運営会社等、第三者が規則を作成し、納品する、という仕様であれば、実質、規則の作成業務を外注しているだけであり、助成対象の改善事業には該当しません。(後者の場合は、運営会社等について社労士法違反の問題も生じ得ます。)
なお、前者の場合、労働能率の増進に資するものであれば支給対象となりますが、就業規則等の作成については、社労士固有の業務であり、本来、有資格者の責任において作成すべきものです。現在、申請事業場では有資格者の労働者が存在しているのか、又は当該労働者にどのような作業をさせており、どの程度作業に時間を有しており、当該サービスを利用することにより、労働者の作業がどの程度軽減されるのか確認する必要があります。
運営会社がクラウド上のソフトウェアの更新や管理を行うのみで、社労士等が本サービスを利用することにより、自ら規則の作成等が行える仕様であれば問題ありませんが、本サービスに情報を入力することにより、当該情報をもとに、運営会社等、第三者が規則を作成し、納品する、という仕様であれば、実質、規則の作成業務を外注しているだけであり、助成対象の改善事業には該当しません。(後者の場合は、運営会社等について社労士法違反の問題も生じ得ます。)
なお、前者の場合、労働能率の増進に資するものであれば支給対象となりますが、就業規則等の作成については、社労士固有の業務であり、本来、有資格者の責任において作成すべきものです。現在、申請事業場では有資格者の労働者が存在しているのか、又は当該労働者にどのような作業をさせており、どの程度作業に時間を有しており、当該サービスを利用することにより、労働者の作業がどの程度軽減されるのか確認する必要があります。
2025.11.11
ドライブレコーダーの導入は、運送業でなくても、労働能率増進に資する設備機器として助成対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによりますが、ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるものの、その導入
が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となるとされています。
「労働能率の増進に資する設備・機器等」かどうかは労働者が直接行う業務負担を軽減する整備・機器等かどうかによりますが、ドライブレコーダー自体は事故等が生じた時の証拠等を確保するためのものではあるものの、その導入
が労働者の業務負担軽減につながるものと認められる特段の事情があれば、助成対象となるとされています。
2025.11.10
交付決定日から支給申請日までのローン支出予定額を助成対象経費にできる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
機械装置等購入費が高額なために月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費とすること(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ 20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4回分合計 100 万円のみを支給対象とする)については、改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できないため、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合は交付決定できないとされています。
機械装置等購入費が高額なために月々ローンを組んで支払うこととし、交付決定日から支給申請日までに支出する予定の金額のみを助成対象経費とすること(たとえば、500 万円の機器を毎月25 万円ずつ 20 回払いで支払う契約をし、交付決定日から支給申請日までに支払った4回分合計 100 万円のみを支給対象とする)については、改善事業は、事業実施予定期間内に納品がなされ、かつ支給申請日までに全額支払いがなされるものでなければ交付決定できないため、支給申請日に一部の代金の支払いしか見込まれない場合は交付決定できないとされています。
2025.11.09
労働能率の増進に資する設備として自動車を購入する場合、スタッドレスタイヤは助成対象経費に含まれる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となります。
寒冷地(積雪地)におけるスタッドレスタイヤの装備については、通常装備品として支給対象となります。
2025.11.08
テレワーク用通信機器の導入・更新費用を助成対象とすることはできる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
テレワーク機器が「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当すれば支給対象となります。
その場合には、当該テレワーク機器が、通勤時間の回避のみならず、仕事そのものの労働能率を増進するものであることの明確で客観的かつ合理的な疎明が必要です。
テレワーク機器が「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に該当すれば支給対象となります。
その場合には、当該テレワーク機器が、通勤時間の回避のみならず、仕事そのものの労働能率を増進するものであることの明確で客観的かつ合理的な疎明が必要です。
2025.11.05
申請事業主の代表者自らが役員を務める別法人が改善事業の受託者となることは認められる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当しますが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断されます。
申請事業主の代表者又は役員が、自ら代表者又は役員を務める別法人の改善事業の受託者となることは、一般的には「受託者となることは認められない場合」に該当しますが、判断に当たっては、両者の関係が、実態として「一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に該当するものか否か」によって判断されます。
2025.11.04
助成金を受給した場合、寄付行為を行うことは可能?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
助成金を受給した場合に寄付行為を行うことは、政治資金規正法第 22 条の3第1項で寄付制限の例外となっているため、差し支えないとされています。
助成金を受給した場合に寄付行為を行うことは、政治資金規正法第 22 条の3第1項で寄付制限の例外となっているため、差し支えないとされています。
2025.11.01
国外企業の見積書において為替レートの取り扱いは?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
国外企業の見積書でも可とされ、交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされます。支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能とされています。
国外企業の見積書でも可とされ、交付申請時に添付する見積書の為替レートは変動するものの、見積時点の為替レートの金額で交付決定がなされます。支給申請までの期間内に支払を行う場合、仮に、交付決定(支出負担行為)額を超える為替レートで支払った場合には、支払時の為替レートに合わせて変更申請を行えば金額変更も可能とされています。
2025.10.31
改善事業において店舗移転と同時期の機器の購入、改良等であっても助成対象となる?
サンライズ社会保険労務士法人のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
改善事業の内容として旧式のレジスターから POS システムへの入れ替えを予定し、当該入れ替えは、元々決まっていた店舗の移転と同時に行いたいと考えている場合、事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であってもそれが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となるとされています。
改善事業の内容として旧式のレジスターから POS システムへの入れ替えを予定し、当該入れ替えは、元々決まっていた店舗の移転と同時に行いたいと考えている場合、事業場移転時と同時期の機器の購入、改良等であってもそれが労働時間の短縮や勤務間インターバルの確実な確保のために資するものであれば、助成対象となるとされています。